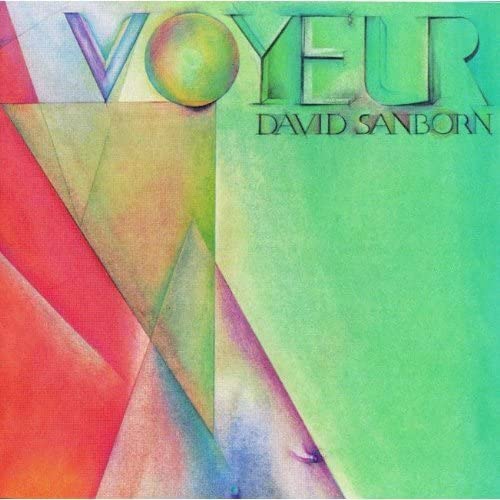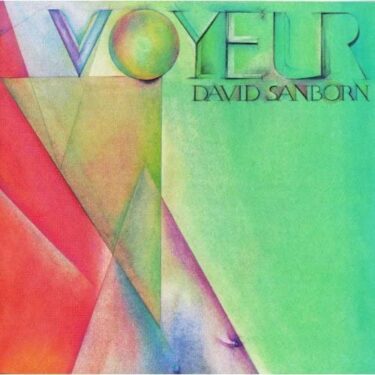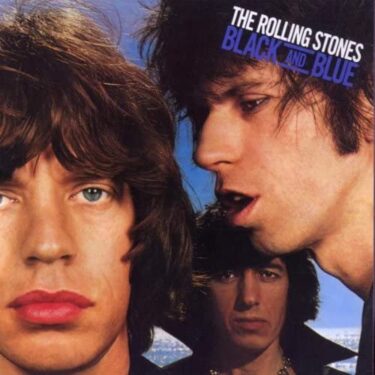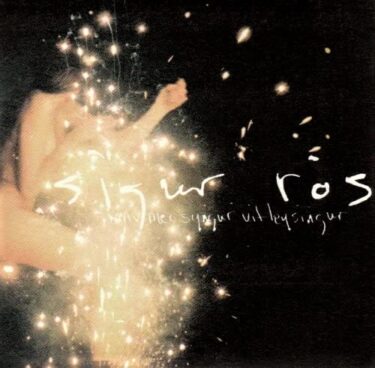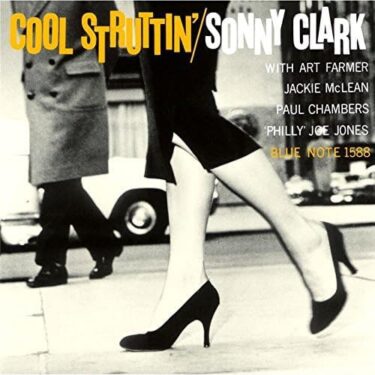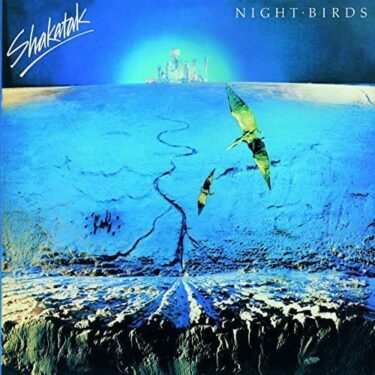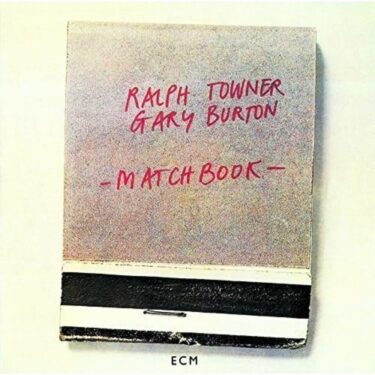今回はデイヴィッド・サンボーンのランキングを作成しました。
この人の音楽はフュージョンやクロスオーバーに分類されます。
しかしそれほど小難しくなく、どちらかというと分かりやすい音楽かもしれません。
単純にプレイヤーとしての表現強者ぶりに圧倒される演奏ばかりです。
- 1 1位「Let’s Just Say Goodbye」(アルバム:Voyeur)
- 2 2位「Anything You Want」(アルバム:Hideaway)
- 3 3位「Run for Cover」(アルバム:Straight to the Heart)
- 4 4位「Rush Hour」(アルバム:As We Speak)
- 5 5位「Lotus Blossom」(アルバム:Straight to the Heart)
- 6 6位「Chicago Song」(アルバム:A Change of Heart)
- 7 7位「Neither One of Us (Wants to Be the First to Say Goodbye)」(アルバム:Backstreet)
- 8 8位「Slam」(アルバム:Close-Up)
- 9 9位「Maputo」(アルバム:Double Vision)
- 10 10位「Bang Bang」(アルバム:Upfront)
- 11 関連記事
- 12 記事一覧
- 13 他ブログ・SNS等
1位「Let’s Just Say Goodbye」(アルバム:Voyeur)
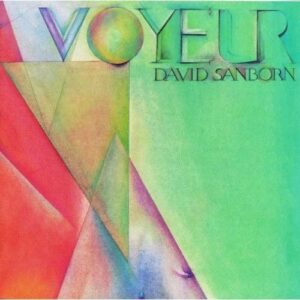
■曲名:Let’s Just Say Goodbye
■曲名邦題:夢魔へ
■アルバム名:Voyeur(1981年)
■アルバム名邦題:夢魔
■動画リンク:「Let’s Just Say Goodbye」
彼はこのアルバムで初めてグラミー賞のベストR&B器楽演奏部門を受賞しました。
確かにこのアルバムはとても充実しています。
グラミー賞を受賞した「オール・アイ・ニード・イズ・ユー(All I Need is You)」や「ウェイク・ミー・ホエン・イッツ・オーヴァー(Wake Me When It’s Over)」など、すばらしい楽曲が収録されています。
後者だけリンクを貼っておきましょう。
David Sanborn – Wake Me When It’s Over
ただアルバム名がかなり奇妙です。
「Voyeur」は「夢魔」という邦題が付けられていますが、直訳では「盗撮」とか「のぞき趣味の人」みたいな意味ですから。
彼の音楽のイメージには合っていないかもしれません。
2位「Anything You Want」(アルバム:Hideaway)
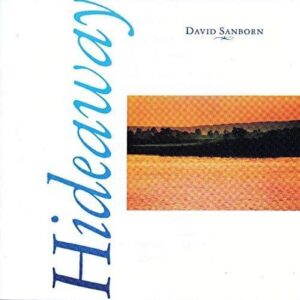
■曲名:Anything You Want
■曲名邦題:エニシング・ユー・ウォント
■アルバム名:Hideaway(1979年)
■アルバム名邦題:ハイダウェイ
■動画リンク:「Anything You Want」
今回は対象期間を、このアルバムから「Upfront」までに限定しました。
そのため以下の初期の作品は対象外になりました。
・「テイキング・オフ(Taking Off)」
・「メロー・サンボーン(David Sanborn)」
・「流麗なる誓い(Promise Me the Moon)」
・「ハート・トゥ・ハート(Heart to Heart)」
ただその時期にも良い曲が沢山あります。
ファースト・アルバムから、1曲だけご紹介しましょう。
既に彼の個性が表れていますね。
しかし本格的に彼の人気がブレイクするには、このアルバムの発表を待たなければいけませんでした。
このアルバムは5作目にしてようやくジャズチャート5位、R&Bチャート33位を記録しました。
他にもバラードの「リサ(Lisa)」など、彼の定番曲が収録されています。
3位「Run for Cover」(アルバム:Straight to the Heart)
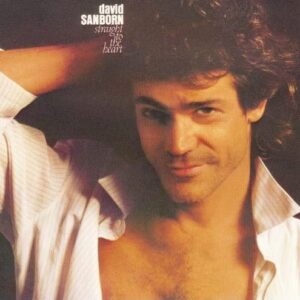
■曲名:Run for Cover
■曲名邦題:ラン・フォー・カヴァー
■アルバム名:Straight to the Heart(1984年)
■アルバム名邦題:ストレイト・トゥ・ザ・ハート(ライヴ!)
■動画リンク:「Run for Cover」
この曲は、マーカス・ミラー(Marcus Miller)のベースが聞きものです。
マーカス・ミラーは「Hideaway」に参加してから、徐々に存在感を高めていきました。
最初はベーシストとして参加しただけでしたが、その後多くの楽曲を提供し始めました。
その後前作「Backstreet」ではマイケル・コリーナ(Michael Colina)とレイ・バーダニ(Ray Bardani)と共にプロデューサーに名を連ね、このアルバムでは単独でプロデュースしています。
サンボーンは、サックス・プレイヤーとしては超一流です。
しかし音楽全体のビジョンを描くことについては、あまり得意ではないかもしれません。
そのせいで実力は申し分ないのに、ブレイクに時間がかかったように思いますし。
しかしこの頃にはマーカス・ミラーがいました。
サンボーンはマーカスに全体の指揮を任せて、自身のプレイに専念した結果この傑作が生まれました。
マーカスは演奏面でも重要な役割を果たしています。
特に1:36からのチョッパーは、いかにもマーカスらしい名演です。
4位「Rush Hour」(アルバム:As We Speak)
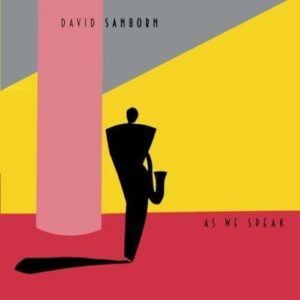
■曲名:Rush Hour
■曲名邦題:ラッシュ・アワー
■アルバム名:As We Speak(1982年)
■アルバム名邦題:ささやくシルエット
■動画リンク:「Rush Hour」
このアルバムの特徴は、マイケル・センベロ(Michael Sembello)が参加していることです。
マイケル・センベロは「フラッシュダンス(Flashdance)」のサウンドトラックで「マニアック(Maniac)」というヒットを飛ばした人。
マイケル・センベロは、ソロでも「マニアック(Bossa Nova Hotel)」というAOR名盤を残しています。
以前サンボーンは「Promise Me the Moon」などで、AORっぽいアプローチをしていました。
このアルバムもAOR色が強いように思います。
そうした印象はマイケル・センベロが「バック・アゲイン(Back Again)」など2曲でボーカルをとっているせいかもしれません。
実際このアルバムはAORファンに人気ですし。
アルバム・ジャケットやアルバム邦題の「ささやくシルエット」も、ボビー・コールドウェル(Bobby Caldwell)っぽい感じがしますね。
この曲はマーカス・ミラーとオマー・ハキム(Omar Hakim)のリズム・セクションが超強力です。
5位「Lotus Blossom」(アルバム:Straight to the Heart)
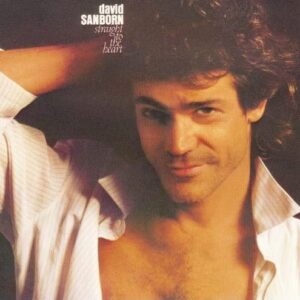
■曲名:Lotus Blossom
■曲名邦題:ロータス・ブロッサム
■アルバム名:Straight to the Heart(1984年)
■アルバム名邦題:ストレイト・トゥ・ザ・ハート(ライヴ!)
■動画リンク:「Lotus Blossom」
「Lotus Blossom」といえば、ケニー・ドーハム(Kenny Dorham)などで知られるジャズ・スタンダードが有名です。
しかしこの曲はDon Grolnickが書いた同名異曲。
さてこのアルバムはサンボーンの最高傑作と言われることが多いですし、私もそう思います。
スタジオ録音では「Hideaway」「Voyeur」のどちらかが最高作だと思います。
しかしこのアルバムはライブ盤でありながら、それらのスタジオ盤と比べて頭一つ抜けているかもしれません。
フュージョンというジャンル全体を見渡しても、屈指の名作といえるでしょう。
さてこの曲はバラードです。
ここまでアップテンポの曲をご紹介してきましたが、バラードでも圧巻の表現力です。
バラードでも全くダレることがありません。
6位「Chicago Song」(アルバム:A Change of Heart)
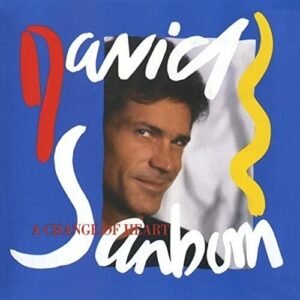
■曲名:Chicago Song
■曲名邦題:シカゴ・ソング
■アルバム名:A Change of Heart(1987年)
■アルバム名邦題:チェンジ・オブ・ハート
■動画リンク:「Chicago Song」
この人の演奏はワンパターンかもしれません。
もちろんある程度バリエーションはありますが、それほどヴァーサタイルなプレイヤーではないように思います。
ただこの人の場合、むしろワンパターンの方が良いかもしれません。
野球でいえば、速球とカーブだけで打者をねじ伏せる怪物ピッチャーみたいな人だと思いますから。
サクソフォニストなら一度はあこがれる、絶対強者感のあるサックス・プレイヤー。
少年ジャンプの主人公みたいな、シンプルにあこがれる実力の持ち主です。
またこの人の魅力は、クセが出まくりなところでしょうか。
特にソウルやファンクのリズムと相性が良く、16ビートでのタメを利かせた演奏が絶品です。
たとえばこの曲では26秒から、ただ簡単なテーマを吹いているのみ。
しかしこんなにシンプルなフレーズにもかかわらず、サンボーンらしさがビシバシ伝わってきますね。
7位「Neither One of Us (Wants to Be the First to Say Goodbye)」(アルバム:Backstreet)
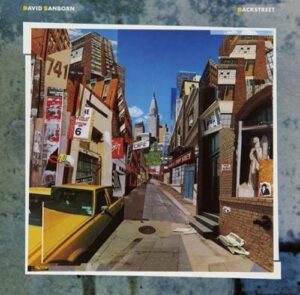
■曲名:Neither One of Us (Wants to Be the First to Say Goodbye)
■曲名邦題:さよならは悲しい言葉
■アルバム名:Backstreet(1983年)
■アルバム名邦題:バックストリート
■動画リンク:「Neither One of Us (Wants to Be the First to Say Goodbye)」
彼のデビューは30歳近くになってからですので、遅咲きの部類だといえるでしょう。
それまではスタジオ・ミュージシャンとして活動してました。
その時代の名演はあまりにも多く、どれもサンボーンらしい刻印が押された演奏ばかり。
たとえば以下のスティーヴィー・ワンダーの「チューズデイ・ハートブレイク」をお聞きください。
Stevie Wonder – Tuesday Heartbreak
サックスの音量がかなり抑えられているのに、すぐにサンボーンだと分かってしまいます(笑)
この人の演奏はいつもそうです。
音の輪郭がはっきりしていて、音のボリュームが低くても他の音より前面に出ていて音の遠近感を狂わせます。
さてこの曲は、グラディス・ナイト&ピップス(Gladys Knight & The Pips)の有名曲のカバー。
ただこの人の場合は自分のアルバム/客演、自作曲/カバー曲などに左右されず、いつでも演奏はマイペースです。
8位「Slam」(アルバム:Close-Up)
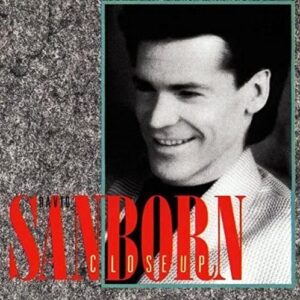
■曲名:Slam
■曲名邦題:スラム
■アルバム名:Close-Up(1988年)
■アルバム名邦題:クローズ・アップ
■動画リンク:「Slam」
このアルバムはヒットしましたが賛否両論がありました。
以前から彼は打ち込みを導入していましたが、この作品では更にその路線が進みました。
正直私も打ち込みのリズムは味気ないと感じます。
ただ彼の演奏自体は好調を維持しているので、彼の演奏だけ聞けば大きな問題はありません。
この曲などは、無機質なリズムと肉感的な上半身が合体した名演です。
ハイラム・ブロック(Hiram Bullock)のギターもすばらしいですし。
他には以下のバラードも秀逸です。
デジタルなサウンドという点で損をしているものの、サンボーンの傑作の1つだと思います。
9位「Maputo」(アルバム:Double Vision)
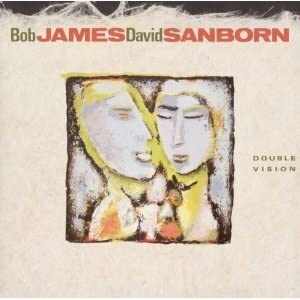
■アーティスト名:Bob James & David Sanborn
■アーティスト名カナ:ボブ・ジェームス & デイヴィッド・サンボーン
■曲名:Maputo
■曲名邦題:マプート
■アルバム名:Double Vision(1986年)
■アルバム名邦題:ダブル・ヴィジョン
■動画リンク:「Maputo」
ボブ・ジェームス(Bob James)との共同名義のアルバムです。
ボブ・ジェームスはファンキーなプレイヤーではなく、激しく濃厚なところが持ち味の人ではありません。
どちらかというとスムース・ジャズに親和性が高い、洗練されたキーボード奏者です。
一方サンボーンは分厚いステーキみたいな人。
その組み合わせの妙は、普段とは違うサンボーンの魅力を浮かび上がらせました。
普段のサンボーンを聞いていると、キメのフレーズが多いと感じます。
ただそれが演奏のメリハリや推進力となって、曲を活性化していました。
しかしここではそうした分かりやすいキメはあまり用いられていません。
スムース・ジャズっぽい曲が多い一方、サンボーンの泣きが引き立っています。
じっくりとサンボーンを聞くならこのアルバムです。
10位「Bang Bang」(アルバム:Upfront)

■曲名:Bang Bang
■曲名邦題:バン・バン
■アルバム名:Upfront(1992年)
■アルバム名邦題:アップフロント
■動画リンク:「Bang Bang」
最後は楽しい曲で締めたいと思います。
この曲はジミー・キャスター(Jimmy Castor)のカバーです。
最後にサンボーンがサックスを始めた経緯をご紹介しましょう。
幼少より小児麻痺にかかり、医師の勧めでリハビリを兼ねてサックスをやり始めた。
リハビリが成功しすぎたかもしれません(笑)
そのせいか彼の音楽には生きる喜びを感じますし、演奏にも泣きはあっても陰りはありません。
ただ純粋に演奏する楽しさが伝わってこないでしょうか。
私はこの人の演奏を聞くと元気が出ます。
もしかしたら本当に疲れたり失意の時には聞けない音楽かもしれません。
ただ少し疲れているぐらいの時にはカンフル剤として抜群の効果を発揮します。
もうひと頑張りしなければいけない方は、がっつりかつ丼でも食べて、サンボーンを聞いてみてはいかがでしょうか。
関連記事
■ブレッカー・ブラザーズ(Brecker Brothers)の名曲名盤10選
■クルセイダーズ(The Crusaders)の名曲名盤10選
■高中正義(Takanaka Masayoshi)の名曲名盤10選
記事一覧
他ブログ・SNS等
■このブログの「トップページ」に戻る
※お気に入りに登録をお願いいたします!
■おとましぐらの音楽ブログ(サブブログ)
※オピニオン記事、企画色の強い記事を連載しています
■note(ジャンル別おすすめ曲一覧)
※選りすぐりの名曲を1曲単位でご紹介しています
■おとましぐらXアカウント
※フォローをお願いいたします!