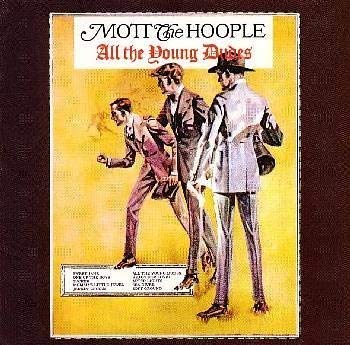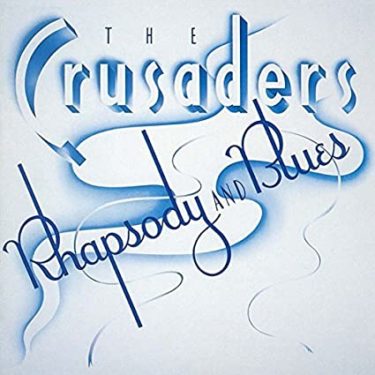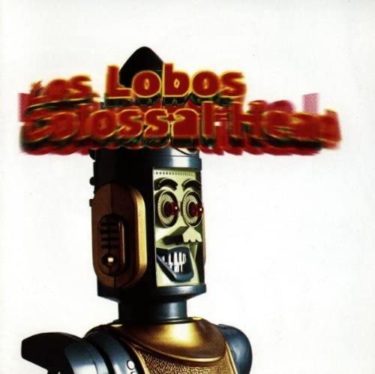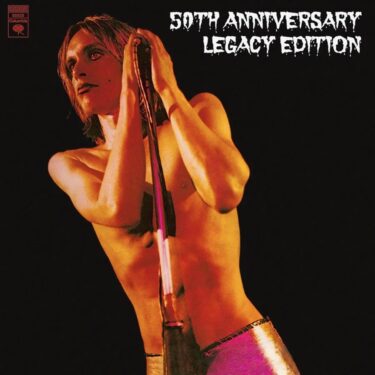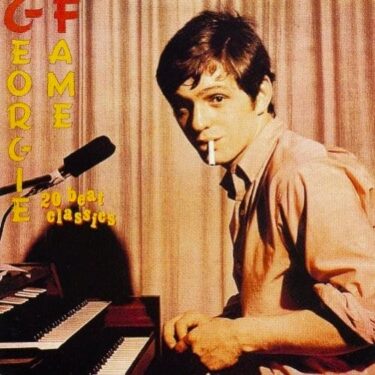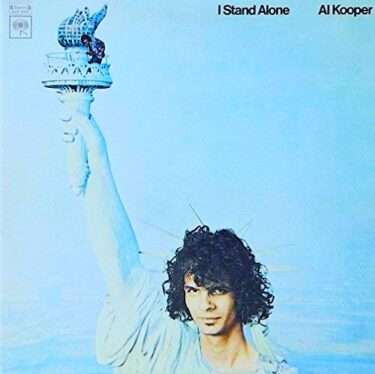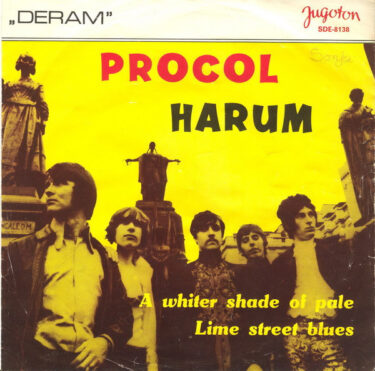今回はモット・ザ・フープルのランキングを作成しました。
このバンドは「グラム・ロック」を象徴するバンドです。
彼らはイエロー・モンキーなど多くの日本のバンドに影響を与えました。
- 1 1位「All the Young Dudes」(アルバム:All the Young Dudes)
- 2 2位「The Golden Age of Rock ‘n’ Roll」(アルバム:The Hoople)
- 3 3位「Jerkin’ Crocus」(アルバム:All the Young Dudes)
- 4 4位「All the Way from Memphis」(アルバム:Mott)
- 5 5位「Sweet Jane」(アルバム:All the Young Dudes)
- 6 6位「Roll Away the Stone」(アルバム:The Hoople)
- 7 7位「Honaloochie Boogie」(アルバム:Mott)
- 8 8位「Marionette」(アルバム:The Hoople)
- 9 9位「Walkin’ with a Mountain」(アルバム:Mad Shadows)
- 10 10位「Sea Diver」(アルバム:All the Young Dudes)
- 11 関連記事
- 12 記事一覧
- 13 他ブログ・SNS等
1位「All the Young Dudes」(アルバム:All the Young Dudes)

■曲名:All the Young Dudes
■曲名邦題:すべての若き野郎ども
■アルバム名:All the Young Dudes(1972年)
■アルバム名邦題:すべての若き野郎ども
■動画リンク:「All the Young Dudes」
無軌道で刹那的な若者の生き方を肯定した曲です。
若者は大人からさげすまれたり、時には一晩中自殺を考えることもあるだろう。
でも俺たちは邪魔されるのはうんざり、好きにやらせてもらうぜという内容です。
ただ当時ボーカルのイアン・ハンター(Ian Hunter)は33歳でしたから、若者代表としては年齢的にギリギリだったかもしれません。
この曲は彼らが解散するという噂を聞きつけたデヴィッド・ボウイから提供されました。
ただ当初ボウイが提供しようとしたのは、名盤「ジギー・スターダスト」に収録予定だった「サフラジェット・シティ(Suffragette City)」。
しかしモット・ザ・フープルがその曲を断ったため、代わりこの曲が提供されたそうです。
この曲は待望の初ヒット(全英3位)になりました。
同曲はボウイのバージョンもあって、そちらもすばらしい出来です。
David Bowie – All the Young Dudes
「すべての若き野郎ども」というアルバム名は、ダムドの「地獄に堕ちた野郎ども」、中村一義の「すべてのバカき野郎ども」など「野郎どもシリーズ」の源流です。
2位「The Golden Age of Rock ‘n’ Roll」(アルバム:The Hoople)
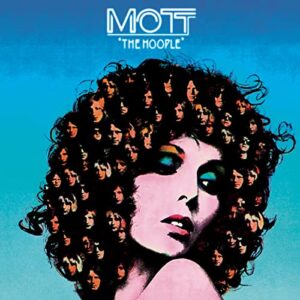
■曲名:The Golden Age of Rock ‘n’ Roll
■曲名邦題:ロックンロール黄金時代
■アルバム名:The Hoople(1974年)
■アルバム名邦題:ロックンロール黄金時代
■動画リンク:「The Golden Age of Rock ‘n’ Roll」
この曲が生まれた背景には「音楽が死んだ日」があると言われています。
「音楽が死んだ日」とは、バディ・ホリー、リッチー・ヴァレンス、J.P.”ビッグ・ボッパー” リチャードソンという、3人のロックンローラーを飛行機事故で失った日のこと。
事故が起こった1959年2月3日は、ロックの歴史が後退した日だと言われています。
この曲を書いたイアン・ハンターは、当時20歳ぐらいでした。
それから年月が経過して、今や彼自身がスターとなり「今がロックンロールの黄金時代だ」と宣言しています。
彼らのロックンロール・ナンバー中でも最高の1曲でしょう。
まさにロックンロールの黄金期を体感できる曲です。
3位「Jerkin’ Crocus」(アルバム:All the Young Dudes)

■曲名:Jerkin’ Crocus
■曲名邦題:ジャーキン・クローカス
■アルバム名:All the Young Dudes(1972年)
■アルバム名邦題:すべての若き野郎ども
■動画リンク:「Jerkin’ Crocus」
この曲は、ミック・ラルフス(Mick Ralphs)によるギターのリフが聞きものです。
B級ローリング・ストーンズ(The Rolling Stones)みたいな感じがたまりません。
デビュー時には既に彼らはストーンズの影響を受けていました。
ただ初期はストレートにその影響を表した曲が多くありません。
彼らがブレイクしたのは、ストーンズの影響をストレートに表現するようになってからです。
今回の記事はストーンズ・ファンにも気に入っていただけそうな曲ばかり選びました。
4位「All the Way from Memphis」(アルバム:Mott)
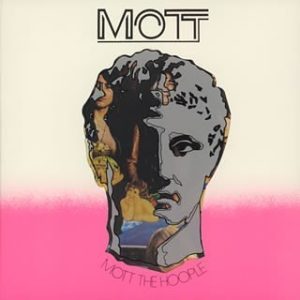
■曲名:All the Way from Memphis
■曲名邦題:メンフィスからの道
■アルバム名:Mott(1973年)
■アルバム名邦題:革命
■動画リンク:「All the Way from Memphis」
この曲ではピアノが大きな役割を果たしています。
小気味良いピアノが、終始曲をリードしていますね。
弾いているのは、この時点ではまだ正式メンバーではなかったモーガン・フィッシャー(Morgan Fisher)。
この人はラヴ・アフェアー(Love Affair)というバンドのメンバーでした。
ラヴ・アフェアーは、以下の曲で知られています。
Love Affair – Everlasting Love
ちなみに彼は1985年に日本に移住して、数多くのCMやアーティストの作品に参加しています。
2:08ぐらいからのサックスも、パーティ・ロックンロールらしく盛り上げてくれます。
この頃のイアン・ハンターは、こういうキャッチーな曲を書くようになっていました。
5位「Sweet Jane」(アルバム:All the Young Dudes)

■曲名:Sweet Jane
■曲名邦題:スウィート・ジェーン
■アルバム名:All the Young Dudes(1972年)
■アルバム名邦題:すべての若き野郎ども
■動画リンク:「Sweet Jane」
この曲のオリジナルは、ヴェルヴェット・アンダーグラウンド(The Velvet Underground)です。
私は作曲面が彼らの弱点だと思います。
しかしロック・バンドとしてのポテンシャルは充分すぎるほどでした。
なにせあのデヴィッドボウイが、デビュー時からのファンだったぐらいですから。
今初期を聞き返しても、演奏面ではとても魅力的です。
しかし初期の彼らには決定的な曲がありません。
アルバムはそれなりに売れた一方、シングルは全然売れませんでした。
このアルバムのプロデュースを買って出たボウイは、カバー曲と自分が提供した曲でその弱点を補いました。
6位「Roll Away the Stone」(アルバム:The Hoople)
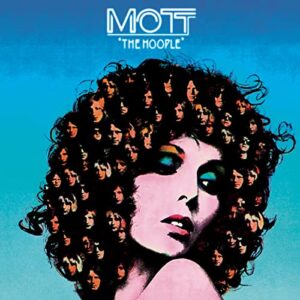
■曲名:Roll Away the Stone
■曲名邦題:土曜日の誘惑
■アルバム名:The Hoople(1974年)
■アルバム名邦題:ロックン・ロール黄金時代
■動画リンク:「Roll Away the Stone」
※アルバムバージョンとは若干違う箇所があります
イアン・ハンターには、こういうドラマティックな曲調を好む人でした。
ただ初期から共にバンドをけん引してきたミック・ラルフスとは相容れませんでした。
ミック・ラルフスは前作の後に脱退して、バッド・カンパニー(Bad Company)というルーツ寄りのバンドを結成しています。
2人は以下の通り、違う道を進むことになりました。
・イアン・ハンター →モット・ザ・フープルに残留
・ミック・ラルフス →バッド・カンパニー結成
渋いブリティシュ・ロックだったバッドカンパニーのファースト・アルバムと、ドラマティックでギラギラしたこのアルバムは、どちらも1974年に発売されています。
よくも水と油のような2人が、同じバンドに在籍していたなと思わずにはいられません。
ミック・ラルフスの脱退は残念ですが、それぞれ傑作を発表したので、結果的に正解だったかもしれません。
7位「Honaloochie Boogie」(アルバム:Mott)
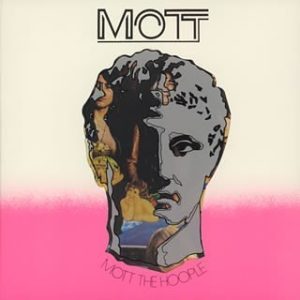
■曲名:Honaloochie Boogie
■曲名邦題:ホナルーチ・ブギ
■アルバム名:Mott(1973年)
■アルバム名邦題:革命
■動画リンク:「Honaloochie Boogie」
彼らは前作「All the Young Dudes」が世界的なヒットを記録しました。
このアルバムはその次作ですが、デヴィッド・ボウイのプロデュースではなく、セルフ・プロデュースです。
ボウイの後ろ盾がなくなったこの作品は、バンドにとって正念場だったといえます。
彼らはこのアルバム前に「Lay Down」というシングルを発表しましたが、チャートには振るいませんでした。
昔の彼らを思わせるような、良質ですが今一歩詰めの足りない感じがします。
彼はアルバムを完成させて、この曲をファースト・シングルとして発表したところ、全英シングルチャートで12位にまで上がりました。
彼らは正念場を、イアン・ハンターが書いたこの曲で乗り切りました。
その間彼らを心配したボウイは「ドライブ・イン・サタディ(Drive In Saturday)」という曲の提を申し出たそうですが、バンド側が断ったそうです。
しかしボウイという人は、本当にいい人なのですね。
8位「Marionette」(アルバム:The Hoople)
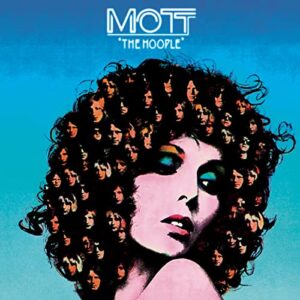
■曲名:Marionette
■曲名邦題:マリオネットの叫び
■アルバム名:The Hoople(1974年)
■アルバム名邦題:ロックン・ロール黄金時代
■動画リンク:「Marionette」
このアルバムは、曲の日本語タイトルが少しやりすぎな感じがします。
「Alice」 →「あばずれアリス」
「Born Late ’58」 →「あの娘はイカしたキャディラック」
そしてこの曲も
「Marionette」→「マリオネットの叫び」
バッドボーイズ風に脚色しすぎな邦題ばかりですね(笑)。
それはともかく、彼らは派手なロックンロールが持ち味のバンドです。
しかしこの曲では構成が凝っていて、演劇っぽい要素を感じます。
おそらく当時はアリス・クーパー(Alice Cooper)の影響を受けていたかもしれません。
この曲の歌詞は、先生のあやつり人形になっている哀れな生徒の話です。
そういえばアリス・クーパーも、学校や先生をディスっていました。
9位「Walkin’ with a Mountain」(アルバム:Mad Shadows)

■曲名:Walkin’ with a Mountain
■曲名邦題:ウォーキン・ウィズ・ア・マウンテン
■アルバム名:Mad Shadows(1970年)
■アルバム名邦題:マッド・シャドウズ
■動画リンク:「Walkin’ with a Mountain」
この記事では時期を限定していません。
ただイアン・ハンターとミック・ラルフスの2人が脱退して、残りメンバーだけでリリースしたアルバムは除外しました。
その2人のいないバンドを、モット・ザ・フープルと呼んでもいいのかと思ってしまいます。
それ以外は時期を絞っていないのにもかかわらず、選曲元のアルバムが偏りました。
彼らはブレイクするまで、以下の4枚のアルバムをリリースしています。
「モット・ザ・フープル(Mott the Hoople)」
「マッド・シャドウズ(Mad Shadows)」
「ワイルドライフ(Wildlife)」
「ブレイン・ケイパーズ(Brain Capers)」
どれも悪くはありませんが、これぞという曲がないように思います。
異論もあると思いますが、私がブレイク後の名曲群に匹敵すると思ったのはこの曲だけです。
この曲は「華麗なる煽動者〜モット・ライブ(Live)」でも取り上げられていますが、私はこのオリジナルの方が良い出来だと思いました。
10位「Sea Diver」(アルバム:All the Young Dudes)

■曲名:Sea Diver
■曲名邦題:潜水夫
■アルバム名:All the Young Dudes(1972年)
■アルバム名邦題:すべての若き野郎ども
■動画リンク:「Sea Diver」
この頃から少しずつイアン・ハンターの存在が大きくなってきました。
情感とドラマ性を備えた彼の歌は、強く人を惹きつけてやみません。
初期の彼はボブ・デイラン(Bob Dylan)からの影響を感じさせました。
後期でも「Mott」の「母になりたい(I Wish I Was Your Mother)」などで、その影響を感じます。
ただ一方で彼にはドラマティックに歌い上げる、初期デヴィッド・ボウイ型のパターンもあります。
この曲は後者を代表する曲。
ソロ・アルバムでも、この路線で曲を量産しています。
このアルバム前バンドはじり貧で、一度は解散を決定しましたが、ボウイの支援を受けて撤回する有様でした。
しかしこのアルバムは起死回生のヒットとなりました。
この曲は神に救済を求めている内容ですが、どうやらその願いは通じたようですね。
関連記事
■ローリング・ストーンズ(The Rolling Stones)の名曲名盤20選
■アリス・クーパー(Alice Cooper)の名曲名盤10選
■エドガー・ウィンター(Edgar Winter)の名曲名盤10選
■モトリー・クルー(Motley Crue)の名曲名盤10選
記事一覧
他ブログ・SNS等
■このブログの「トップページ」に戻る
※お気に入りに登録をお願いいたします!
■おとましぐらの音楽ブログ(サブブログ)
※オピニオン記事、企画色の強い記事を連載しています
■note(ジャンル別おすすめ曲一覧)
※選りすぐりの名曲を1曲単位でご紹介しています
■おとましぐらXアカウント
※フォローをお願いいたします!