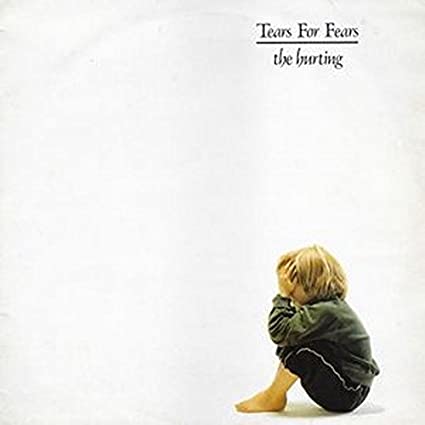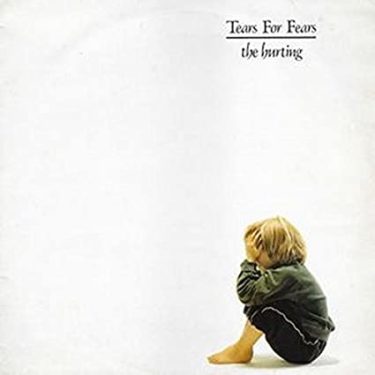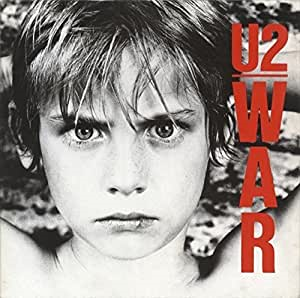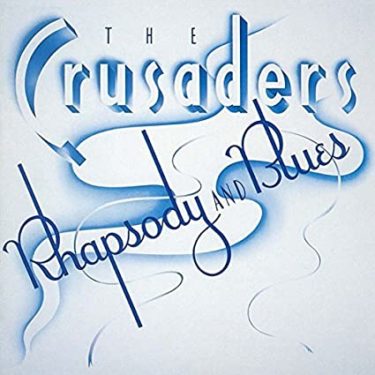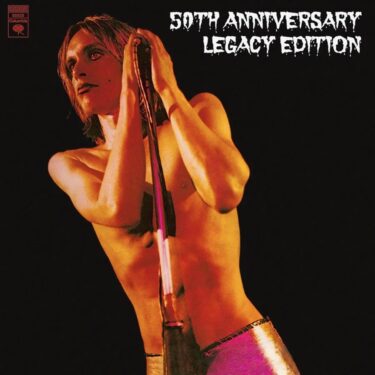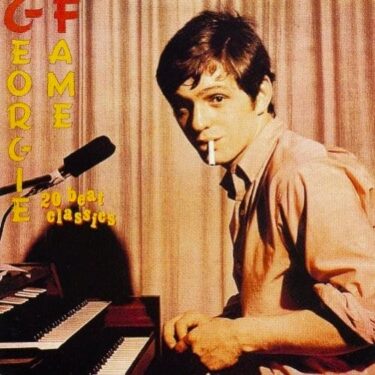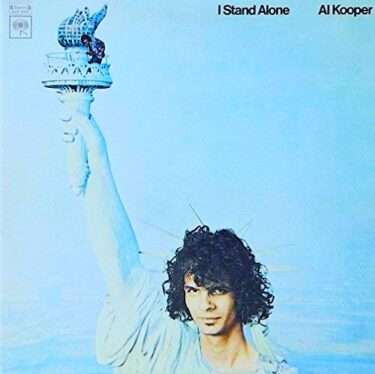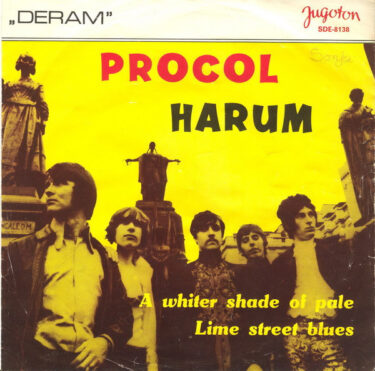今回はティアーズ・フォー・フィアーズのランキングを作成しました。
彼らのバンド名は、アーサー・ヤノフ(Arthur Janov)という心理学者の精神療法に由来しています。
叫ぶことで抑圧された心の傷を昇華しようという考え方から名付けられています。
彼らは叫ぶ代わりに歌うことで、不幸な記憶を乗り越えようとしました。
今、辛い状況に置かれた人におすすめしたい音楽です。
- 1 1位「Sowing the Seeds of Love」(アルバム:The Seeds of Love)
- 2 2位「Everybody Wants to Rule the World」(アルバム:Songs From The Big Chair)
- 3 3位「Shout」(アルバム:Songs From The Big Chair)
- 4 4位「Pale Shelter」(アルバム:The Hurting)
- 5 5位「Advice for the Young at Heart」(アルバム:The Seeds of Love)
- 6 6位「Mad World」(アルバム:The Hurting)
- 7 7位「Head over Heels」(アルバム:Songs From The Big Chair)
- 8 8位「Change」(アルバム:The Hurting)
- 9 9位「Goodnight Song」(アルバム:Elemental)
- 10 10位「Closest Thing to Heaven」(アルバム:Everybody Loves A Happy Ending)
- 11 関連記事
- 12 記事一覧
- 13 他ブログ・SNS等
1位「Sowing the Seeds of Love」(アルバム:The Seeds of Love)

■曲名:Sowing the Seeds of Love
■曲名邦題:シーズ・オブ・ラヴ
■アルバム名:The Seeds of Love(1989年)
■アルバム名邦題:シーズ・オブ・ラヴ
■動画リンク:「Sowing the Seeds of Love」
この曲は発表当時から、ビートルズの影響を受けていると言われていました。
確かに愛の大切さを訴えるメッセージとアレンジは、ビートルズを意識しているように感じます。
アルバム・ジャケットを見て、ビートルズの覆面バンドと噂されたクラトゥ(Klaatu)を思い出す人もいるかもしれません。
この曲ができた背景には、当時の政治状況があるといわれています。
当時イギリスは、サッチャー首相率いる保守党が圧倒的な人気でした。
ローランドはその風潮に不満だったようです。
当時サッチャー首相は、貧富の差を拡大する改革を推し進めていました。
この曲ではそうした改革に対して異を唱える一方で、僕たちは愛の種を蒔こうと訴えています。
ローランドのたくましい歌唱が魅力の曲です。
2位「Everybody Wants to Rule the World」(アルバム:Songs From The Big Chair)
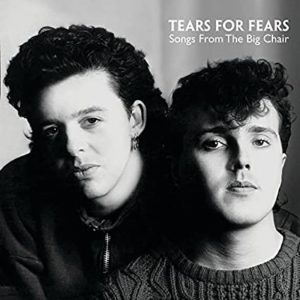
■曲名:Everybody Wants to Rule the World
■曲名邦題:ルール・ザ・ワールド
■アルバム名:Songs From The Big Chair(1985年)
■アルバム名邦題:シャウト
■動画リンク:「Everybody Wants to Rule the World」
まず曲名が穏やかではありません。
曲名を直訳すると「誰もが世界を支配したがっている」。
自由や楽しいことは永続しない。だって誰もが世界を支配したがっているのだからと歌われています。
こういう皮肉的なテーマは、ローランド・オーザバル(Roland Orzabal)の気質を反映していると思われます。
ただ彼だけでなく、とかくイギリス人は皮肉屋で気難しいと言われます。
その意味でこの曲はイギリス人らしい歌詞といえるかもしれません。
実際この曲は、イギリス版グラミー賞の最優秀シングルを受賞しています。
3位「Shout」(アルバム:Songs From The Big Chair)
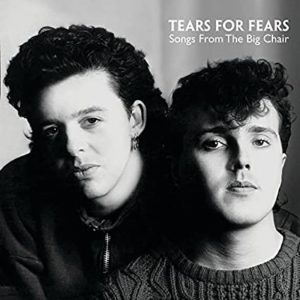
■曲名:Shout
■曲名邦題:シャウト
■アルバム名:Songs From The Big Chair(1985年)
■アルバム名邦題:シャウト
■動画リンク:「Shout」
この曲はアルバムのファースト・シングルではありません。
ファースト・シングルは「マザーズ・トーク(Mothers Talk)」で、この曲はセカンド・シングルです。
この曲は冒頭でご紹介したヤノフの「プライマル・スクリーム療法」を表現した曲といえるかもしれません。
「プライマル・スクリーム療法」とは、ジョン・レノン(John Lennon)が「ジョンの魂(John Lennon/Plastic Ono Band)」のレコーディング中に実践していたことで知られています。
叫んだり表現することによって、心の傷を昇華しようする考え方です。
この曲では「さあ叫べ」と訴えていますね。
ちなみに「Everybody Wants to Rule the World」ではカート・スミス(Curt Smith)がメイン・ボーカルでしたが、こちらはローランドがメイン・ボーカルを務めています。
カートの方が音域が高くイノセントですが、ローランドの声には重厚な説得力と力強さがあります。
この曲はローランド向きの曲かもしれません。
4位「Pale Shelter」(アルバム:The Hurting)
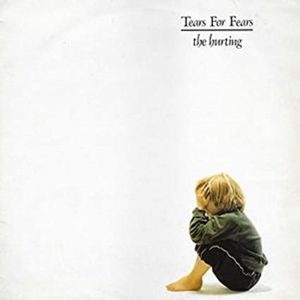
■曲名:Pale Shelter
■曲名邦題:ペイル・シェルター
■アルバム名:The Hurting(1983年)
■アルバム名邦題:ザ・ハーティング
■動画リンク:「Pale Shelter」
このファースト・アルバムのアルバム名「Hurting」は「傷つける」という意味です。
アルバム・ジャケットにも泣いている様子の子供が使われていますね。
あなたは愛を与えず、脆弱な避難所を与えただけと歌われています。
「Pale」をどう訳すのか難しいのですが、青ざめたとか弱々しいとか、そういうネガティブな意味合いの言葉です。
「Pale Shelter」は「不幸な家庭環境」と考えていいかもしれません。
ちなみにローランドとカートの2人は、共に離婚した家庭で育ったという共通点があり、13歳からの友達らしいです。
そのせいか特に初期の曲には、不幸な家庭に育ち心に傷を負った子供の視点が多いように感じます。
5位「Advice for the Young at Heart」(アルバム:The Seeds of Love)

■曲名:Advice for the Young at Heart
■曲名邦題:アドヴァイス・フォー・ザ・ヤング・アット・ハート
■アルバム名:The Seeds of Love(1989年)
■アルバム名邦題:シーズ・オブ・ラヴ
■動画リンク:「Advice for the Young at Heart」
このサード・アルバムでは曲が長くなり、アレンジが多彩になりました。
オリータ・アダムス(Oleta Adams)のボーカルが大きくフィーチャーされ、「ウーマン・イン・チェインズ(Woman in Chains)」など、ホワイト・ソウルといえそうな曲が散見されます。
この曲もそういう1曲。
ただ当時2人の関係はかなり悪化していたようです。
実際このアルバム後、カートはローランドに相談することなく一方的に脱退を宣言しました。
彼らの曲の多くはローランドが中心に書いた曲ですが、前作までローランドは様々な人と共作していて、バランスが取れていたと思います。
しかしこのアルバムでローランドはニッキー ホランド(Nicky Holland)との曲づくりが増え、8曲中5曲を共作しています。
一方カートとの共作は1曲のみ。
ただソロ作でのカートの曲を聞くと、カート自身も優れたソングライターであることが分かります。
カートは自分が冷遇される状況に、相当不満が溜まっていたのではないでしょうか。
6位「Mad World」(アルバム:The Hurting)
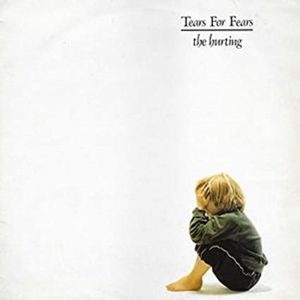
■曲名:Mad World
■曲名邦題:狂気の世界
■アルバム名:The Hurting(1983年)
■アルバム名邦題:ザ・ハーティング
■動画リンク:「Mad World」
この曲では、毎日全力で努力しなければ生き残れないなんて、なんと狂った世界かと訴えています。
歌詞にはこんな箇所もあります。
とても不可解で悲しいことだけど、今まで見た中で最高の夢は、自分が死ぬ夢だ
言いにくいことは分かっているが、あえて言わせてもらう
みんな必死で輪の中をぐるぐる走り回っているけれど、そんなことは僕には受け入れ難い
本当に狂った世界だよ
このアルバムは1983年にリリースされましたが、今の日本も近い状況かもしれません。
7位「Head over Heels」(アルバム:Songs From The Big Chair)
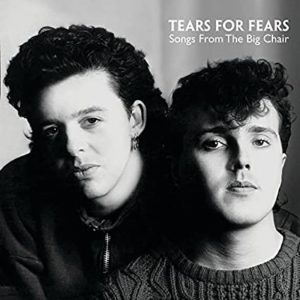
■曲名:Head over Heels
■曲名邦題:ヘッド・オーヴァー・ヒールズ
■アルバム名:Songs From The Big Chair(1985年)
■アルバム名邦題:シャウト
■動画リンク:「Head over Heels」
「Head over Heels」とは「あの娘にぞっこん」みたいな意味なのだそうです。
彼らにしては珍しいラブ・ソングですが、たまにはこういう曲があってもいいと思います。
この頃彼らは、23~24歳の若者でしたから。
さてファーストは繊細なエレポップ路線でしたが、彼らはこのアルバムでロック色を強め、サウンド・プロダクションの強化に成功しています。
それによって世界的なヒットを生み出む下地ができ上がりました。
その変化に貢献したのは、プロデューサーのクリス・ヒューズ(Chris Hughes)。
クリスはファーストでもプロデューサーの1人でしたが、今作では単独でプロデュースを担当しています。
ちなみにクリスの他のプロデュース作はプロパガンダ(Propaganda)、ワン・チャン(Wang Chung)、ハワード・ジョーンズ(Howard Jones)など。
ティアーズ・フォー・フィアーズとも相性が良さそうな感じがしますね。
8位「Change」(アルバム:The Hurting)
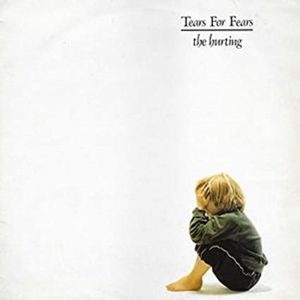
■曲名:Change
■曲名邦題:チェンジ
■アルバム名:The Hurting(1983年)
■アルバム名邦題:ザ・ハーティング
■動画リンク:「Change」
彼らは本国イギリスでは、ファースト・アルバムの時点でアルバム・チャートの1位を記録していました。
ただ世界的な人気を獲得するには至っていませんでした。
このアルバムがリリースされた1983年のイギリスは、エレポップの全盛期です。
■1982年
デュラン・デュラン(Duran Duran)が「リオ(Rio)」を発表
カジャグーグー(Kajagoogoo)が「君はTOO SHY(Too Shy)」を発表
ABCが「ルック・オブ・ラヴ (The Lexicon of Love)」を発表
■1983年
スパンダー・バレエ(Spandau Ballet))が「トゥルー(True)」を発表
上記は全てイギリスのバンドです。
この曲は正統派エレポップですが、彼らは時代の波にうまく乗れたように思います。
9位「Goodnight Song」(アルバム:Elemental)
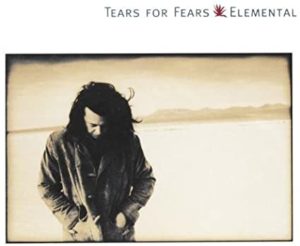
■曲名:Goodnight Song
■曲名邦題:グッドナイト・ソング
■アルバム名:Elemental(1993年)
■アルバム名邦題:ブレイク・イット・ダウン・アゲイン
■動画リンク:「Goodnight Song」
このアルバムは「The Seeds of Love」から4年が経過した1993年にリリースされています。
たった4年間ですが、その間音楽シーンは大きく様変わりをしていました。
たとえば、以下のような転換点となる作品の登場です。
■1989年
ストーン・ローゼズ(The Stone Roses)がデビュー・アルバムを発表
■1991年
プライマル・スクリーム(Primal Scream)が「スクリーマデリカ(Screamadelica)」を発表
これらの作品によって、1980年代の音楽は急速に過去の遺物になろうとしていました。
そうした変化もあって、このアルバムも時代との間にズレが生じてきたような気がします。
ただこの曲や「Break It Down Again」など、個々の曲の出来は申し分ありません。
Tears for Fears – Break It Down Again
10位「Closest Thing to Heaven」(アルバム:Everybody Loves A Happy Ending)
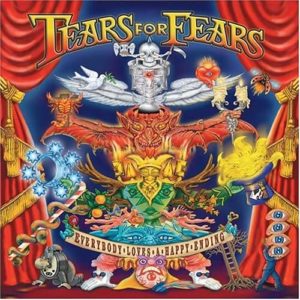
■曲名:Closest Thing to Heaven
■アルバム名:Everybody Loves A Happy Ending(2004年)
■動画リンク:「Closest Thing to Heaven」
このアルバムではカート・スミスが復帰しています。
彼らはカートが脱退してから、別々に音楽活動を続けていました。
両者は共に健闘していたと思いますが、本領を発揮している感じはしませんでした。
しかし彼らは再び合流して、このアルバムをつくり上げます。
2人には組み合わせの妙があるかもしれません。
この曲のメイン・ボーカルはローランドです。
そこにカートのコーラスが加わっただけで、収まるべきところに収まったように感じます。
関連記事
■デュラン・デュラン(Duran Duran)の名曲名盤10選
■スクリッティ・ポリッティ(Scritti Politti)の名曲名盤10選
記事一覧
他ブログ・SNS等
■このブログの「トップページ」に戻る
※お気に入りに登録をお願いいたします!
■おとましぐらの音楽ブログ(サブブログ)
※オピニオン記事、企画色の強い記事を連載しています
■note(ジャンル別おすすめ曲一覧)
※選りすぐりの名曲を1曲単位でご紹介しています
■おとましぐらXアカウント
※フォローをお願いいたします!