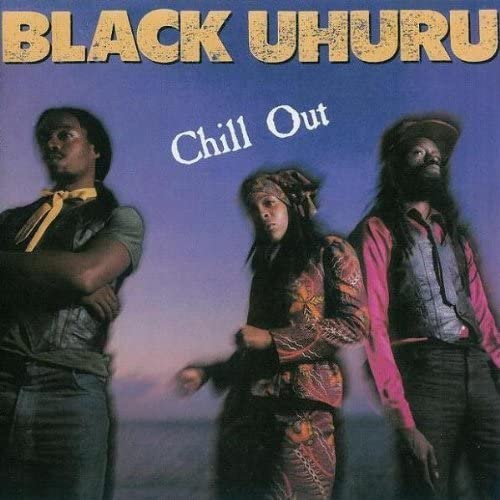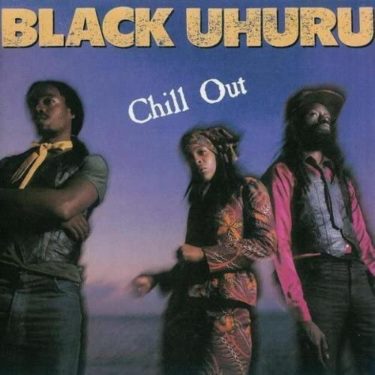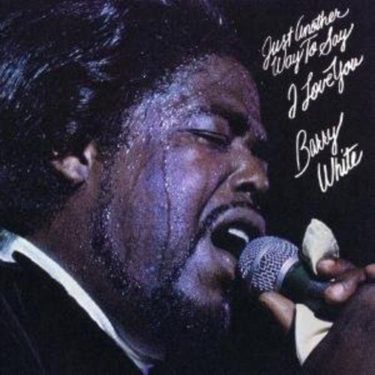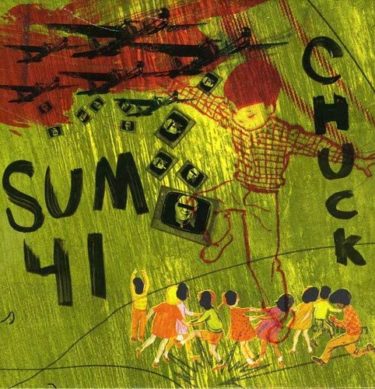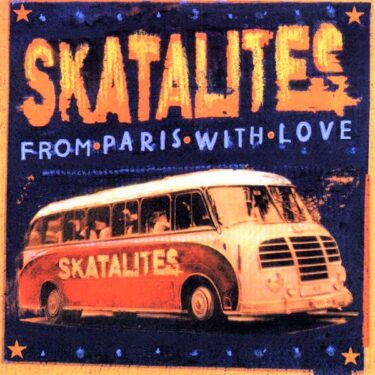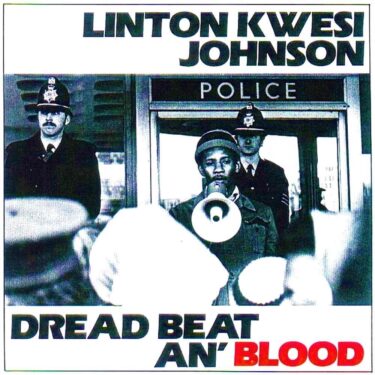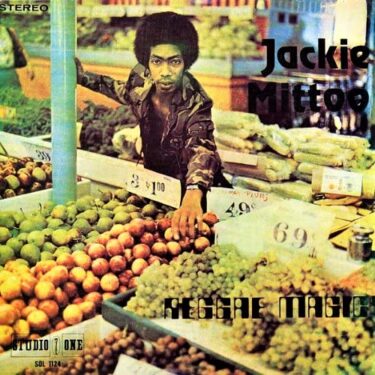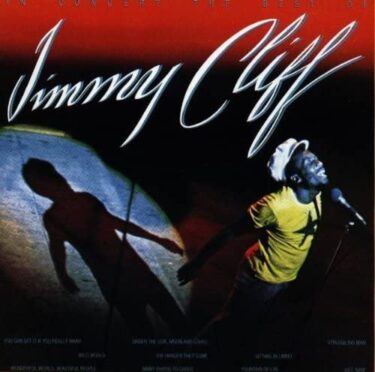今回はブラック・ウフルのランキングを作成しました。
当初彼らはルーツ・レゲエのバンドでしたが、その後徐々にニューウェーヴ色を強めていきました。
この記事ではその刺激的な時期を中心に取り上げています。
レゲエ・ファンはもちろん、ロック・ファンの方にも聞いていただきたいと思います。
- 1 1位「Black Uhuru Anthem」(アルバム:Anthem)
- 2 2位「Sistren」(アルバム:Red)
- 3 3位「I Create」(アルバム:Positive)
- 4 4位「Sponji Reggae」(アルバム:Red)
- 5 5位「Right Stuff」(アルバム:Chill Out)
- 6 6位「Vampire」(アルバム:Sinsemilla)
- 7 7位「Chill Out」(アルバム:Chill Out)
- 8 8位「Elements」(アルバム:Anthem)
- 9 9位「Youth of Eglington」(アルバム:Red)
- 10 10位「What Is Life?」(アルバム:Anthem)
- 11 関連記事
- 12 記事一覧
- 13 他ブログ・SNS等
1位「Black Uhuru Anthem」(アルバム:Anthem)
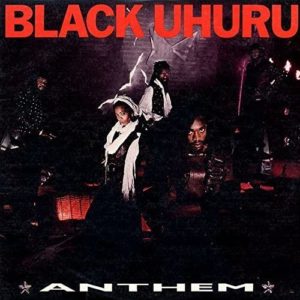
■曲名:Black Uhuru Anthem
■曲名邦題:ブラック・ウフルー・アンセム
■アルバム名:Anthem(1983年)
■アルバム名邦題:アンセム
■動画リンク:「Black Uhuru Anthem」
このグループは「Red」「Chill Out」「Anthem」の三部作が全盛期と言われています。
特にこのアルバムは、グラミー賞の最優秀レゲエ・アルバムを受賞しています。
しかし看板シンガーのマイケル・ローズ(Michael Rose)は、このアルバムを最後に脱退しました。
なんでもダッキー・シンプソン(Derrick “Duckie” Simpson)との関係が悪化したのだとか。
ただ私は音楽的な理由もあったのではないかと推測しています。
というのは、マイケルの初ソロアルバム「プラウド(Proud)」を聞くと、HOUSEやHIPHOP色が強まっていて、大幅に路線を変更したからです。
一方ブラック・ウフルも音楽性を変えましたが、目指していた方向性は異なります。
この曲はマイケルが置き土産として残した曲。
マイケルの声は哀愁漂うこの曲にとてもよく合っています。
2位「Sistren」(アルバム:Red)
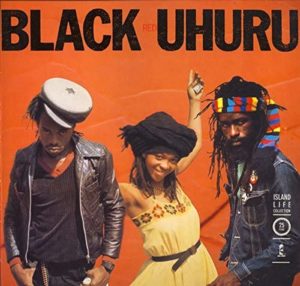
■曲名:Sistren
■曲名邦題:シストリン
■アルバム名:Red(1981年)
■アルバム名邦題:レッド
■動画リンク:「Sistren」
この曲はあまり話題になることはありませんが、私は大好きな曲です。
この曲の魅力はリズムです。
リズムを担当するのは、当時レゲエというジャンルを超えて活躍していたスライ&ロビー(Sly and Robbie)の2人。
ドラム:スライ・ダンバー(Sly Dunbar)
ベース:ロビー・シェイクスピア(Robbie Shakespeare)
この曲はリズムが主役で、特にロビーのベースが大活躍しています。
チョッパーっぽいフレーズを織り交ぜながら躍動していますね。まさに変幻自在。
ドラムのスライ・ダンパーもすばらしく、時々入るダブの残響処理も大変スリリングです。
3位「I Create」(アルバム:Positive)

■曲名:I Create
■曲名邦題:アイ・クリエイト
■アルバム名:Positive(1987年)
■アルバム名邦題:ポジティヴ
■動画リンク:「I Create」
この時期彼らは過渡期にありました。
前々作を最後にマイケル・ローズが脱退し、前作の後にはピューマ・ジョーンズ(Puma Jones)が、病気を理由に脱退しています。
マイケルの後任はジュニア・リード(Junior Reid)、ピューマ・ジョーンズの後任はオラファンケ(Olafunke)。
ジュニア・リードであればマイケルの後釜としてはうってつけです。
またピューマ・ジョーンズは愛らしい存在でしたが、ソロでボーカルをとるタイプではありませんでした。
その点オラファンケは、ソロでボーカルを担当できました。
人気メンバーが脱退した代わりに、グループ表現の幅は広がったかもしれません。
前作「ブルータル(Brutal)」はヒット曲「グレイト・トレイン・ロバリー(Great Train Robbery)」が収録されていますし、それほど悪い出来ではありませんでした。
しかし私はルーツ色が強いこの作品の方に軍配を挙げたいと思います。
この曲で彼らは、悲惨なこの世界で創造することの意味を問いかけています。
4位「Sponji Reggae」(アルバム:Red)
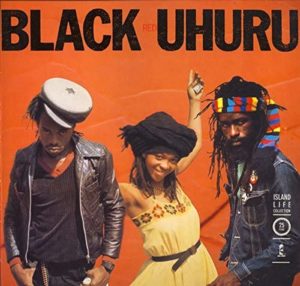
■曲名:Sponji Reggae
■曲名邦題:スポンジ・レゲエ
■アルバム名:Red(1981年)
■アルバム名邦題:レッド
■動画リンク:「Sponji Reggae」
まず「スポンジ・レゲエ」という曲名が何を指しているのか、歌詞を読んでも分かりませんでした。
スポンジは中身がスカスカですから、当時のレゲエ・シーンを批判しているという人もいます。
彼らはレゲエ・ファンにも人気がありますが、ロック・リスナーにも高く評価されています。
彼らは元々、硬派のルーツ・レゲエから始まりました。
初期の「ブラック・サウンズ・オブ・フリーダム(Black Sounds of Freedom)」「ゲス・フーズ・カミング・トゥ・ディナー(Guess Who’s Coming To Dinner)」では、ルーツ色の強い音楽性でした。
私はロック系のリスナーでコンシャスなルーツ・レゲエを好む人は多くないと感じています。
彼らはニューウェーヴ色を強め、ロック系リスナーの注目を浴び始めました。
またこの曲のように分かりやすい楽曲も魅力的でした。
5位「Right Stuff」(アルバム:Chill Out)
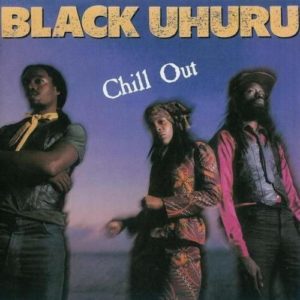
■曲名:Right Stuff
■曲名邦題:ライフ・スタッフ
■アルバム名:Chill Out(1982年)
■アルバム名邦題:チル・アウト
■動画リンク:「Right Stuff」
ニューウェーブ・ファンクといえる曲です。
ミッドナイト・スター(Midnight Star)みたいなボコーダーが特徴的ですね。
このアルバムは特にニューウェーヴ色が強く、この曲のように普通のレゲエとは少し違った曲が多いです。
アルバム・タイトル「Chill Out」は「落ち着け」みたいな意味ですが、むしろ刺激的といえるかもしれません。
その分正統派レゲエファンには、賛否が分かれたかもしれませんが。
今回私が聞きなおして最も再発見が多かったのが、このアルバムです。
後でこのアルバムからもう1曲、タイトル曲をご紹介しています。
もしこの2曲が気に入ったら、アルバム単位でチェックしてみてください。
6位「Vampire」(アルバム:Sinsemilla)
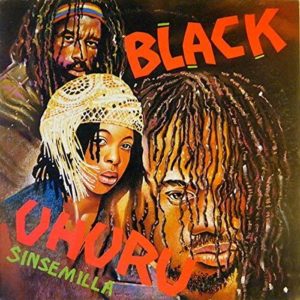
■曲名:Vampire
■曲名邦題:ヴァンパイア
■アルバム名:Sinsemilla(1980年)
■アルバム名邦題:シンセミラ
■動画リンク:「Vampire」
1980年アイランド・レコード(Island Records)からリリースされたアルバムです。
当時同じくアイランド所属のボブ・マーリー(Bob Marley)は、世界的な人気を獲得していました。
アイランドは新しいレゲエのスターを発掘しようし、彼らは後継者候補として期待されていたようです。
彼らはその期待に応えて、すばらしいアルバムをつくり上げました。
このアルバムは以前のアルバムと違って、ポップな音楽性を打ち出しています。
「Red」始めとした全盛期の音楽性は、このアルバムから始まったといってもいいでしょう。
私があまり好きではないシンセ・ドラムが入っているので、個人的にはその点がマイナスですが。
この曲以外では、以下もおすすめです。
ちなみに「Sinsemilla」とは「催眠性の高いマリファナ」のことだそうです。
そのせいかジャケットの3人も、少し眠たそうに見えますね。
7位「Chill Out」(アルバム:Chill Out)
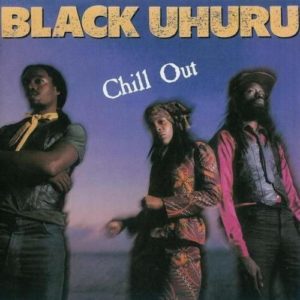
■曲名:Chill Out
■曲名邦題:チル・アウト
■アルバム名:Chill Out(1982年)
■アルバム名邦題:チル・アウト
■動画リンク:「Chill Out」
この曲も典型的なレゲエのリズムとは言い難いかもしれません。
レゲエという音楽は、ディープなボーカルやコーラス、ダブなど様々な聞きどころがあります。
しかし最大の聞きどころは、リズムの妙味ではないでしょうか。
レゲエのリズムについて、裏拍が強調されたスチャ・スチャみたいなものを想像する人が少なくないかもしれません。
ど真ん中のレゲエのリズムみたいなものもありますが、必ずしもそういうものばかりではありません。
ダンス・ホールレゲエの曲を聞くと、全く違う世界ですし。
いっそのことレゲエとは多様なリズム・アプローチの音楽だと思った方がいいかもしれません。
この曲ではゴリゴリと低くうごめくベースが心地よいです。
8位「Elements」(アルバム:Anthem)
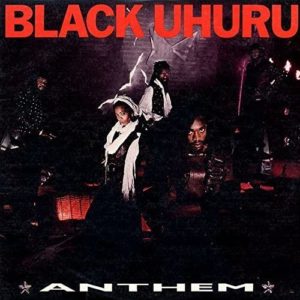
■曲名:Elements
■曲名邦題:エレメンツ
■アルバム名:Anthem(1983年)
■アルバム名邦題:アンセム
■動画リンク:「Elements」
コアなレゲエファンと話すと、音楽が好きなだけでないと感じることがあります。
レゲエは、とても人間らしい音楽だと思います。
またレゲエの歌詞を読むと、我々はバビロン・システムの下で抑圧されているという設定が多いかもしれません。
よくルーツ・レゲエの曲に陰鬱な曲がありますが、そういう曲は抑圧された状況を表現していたりします。
その支配を打破しようと訴えるののが、典型的な歌詞の内容です。
彼らは打開したその先に、より人間らしい喜びの世界があると考えているようですね。
この歌詞でも、自然の美しさや愛がもたらす喜び、その一方で明日のパンを得る為に戦おうと訴えています。
ちなみに「Black Uhuru」の「Uhuru」は、スワヒリ語で「自由」という意味です。
グループ名は「黒人の自由」みたいな感じでしょうか。
9位「Youth of Eglington」(アルバム:Red)
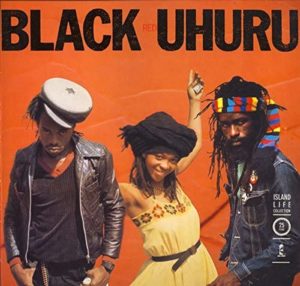
■曲名:Youth of Eglington
■曲名邦題:エリントンの青春
■アルバム名:Red(1981年)
■アルバム名邦題:レッド
■動画リンク:「Youth of Eglington」
今回聞きなおして、やはりこのアルバムが最高傑作だと再確認しました。
RollingStone誌の「1980年代の最高のアルバム100枚」でも23位にランクインしていますし。
中でもこの曲は、先程挙げた「スポンジ・レゲエ」と並ぶ彼らの有名曲です。
このアルバムは他にも取り上げたい曲が多く、特にアルバムのA面にあたる4曲は強力な曲がそろっています。
惜しくもご紹介できなかった曲も、リンクだけ貼っておきましょう。
この曲は彼らの中でも、特にダンスホールで機能しそうな曲の1つです。
私は長年この曲のエリントンとは、デューク・エリントン(Duke Ellington)のことかと思っていました。
しかし先程スペルを見たところ、綴りが違うことに気が付きました。
この曲の「Eglington」とは都市の名前で、その地で生きることの過酷さが歌われています。
10位「What Is Life?」(アルバム:Anthem)
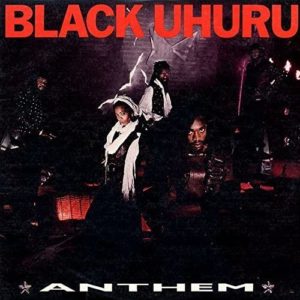
■曲名:What Is Life?
■曲名邦題:ホワット・イズ・ライフ
■アルバム名:Anthem(1983年)
■アルバム名邦題:アンセム
■動画リンク:「What Is Life?」
最後にピューマ・ジョーンズについて触れておきたいと思います。
デリック・シンプソンやマイケル・ローズはジャマイカ人ですが、彼女はアメリカ人です。
彼女はアメリカで生まれ、コロンビア大学を卒業しています。
コロンビア大学は世界の大学ランキングで16位で、東京大学は36位。
彼女は優秀な頭脳を持ったエリートと呼ばれてもいいかもしれません。
しかも彼女は修士ですから博士課程に進めば、教授になる可能性さえありました。
将来の成功は約束されていたことでしょう。
しかし彼女はソーシャル・ワーカーの道を選びました。
ソーシャル・ワーカーとは、生活に困っていたり、問題を抱えている人を支援する仕事です。
あえてその仕事を選んだところに、彼女の人間性がうかがえるかもしれません。
その後彼女は自分のルーツを見つけたいと思い、ジャマイカに移住することにしました。
そこで彼女はブラック・ウフルに参加することになりました。
しかし彼女は「Positive」のレコーディング前に乳がんが見つかり、グループから脱退することになります。
彼女は1990年、36歳の若さで亡くなりました。
この曲の歌詞では「人生とは何か」と問いかけています。
やはりここでも「生き残るためには戦わなければいけない」と訴えています。
曲の最後では「人生はごちそうだ」と締めくくられていますが、とても良い言葉ですね。
関連記事
■リントン・クウェシ・ジョンソン(Linton Kwesi Johnson)の名曲名盤10選
記事一覧
他ブログ・SNS等
■このブログの「トップページ」に戻る
※お気に入りに登録をお願いいたします!
■おとましぐらの音楽ブログ(サブブログ)
※オピニオン記事、企画色の強い記事を連載しています
■note(ジャンル別おすすめ曲一覧)
※選りすぐりの名曲を1曲単位でご紹介しています
■おとましぐらXアカウント
※フォローをお願いいたします!